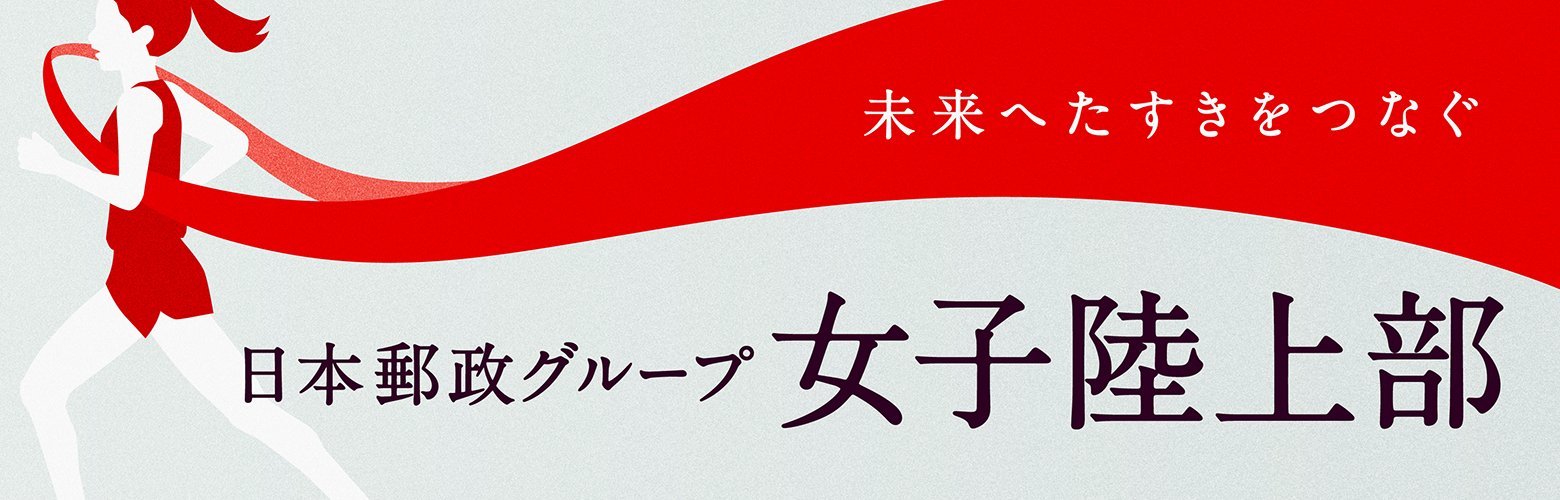健康増進を支援し続けて1世紀。「ラジオ体操」普及推進に取り組む、かんぽ生命の最前線

INDEX
株式会社かんぽ生命保険が2021年に実施した一般消費者調査によると、国内での「ラジオ体操」の認知率は驚異の96.9%――国民的エクササイズの域を超えた、日本の文化といっても過言ではないでしょう。「腕を前から上に上げて、大きく、背伸びの運動~♪」というフレーズとピアノの音色を聞けば、自然と体が動く人も多いはずです。
今回は、ラジオ体操の普及に取り組むかんぽ生命の山口 義文(やまぐち よしふみ)さん、五日市 祐子(いつかいち ゆうこ)さん、谷杉 咲代(たにすぎ さよ)さんに、ラジオ体操が長く親しまれる理由やこれからの展望などを伺いました。
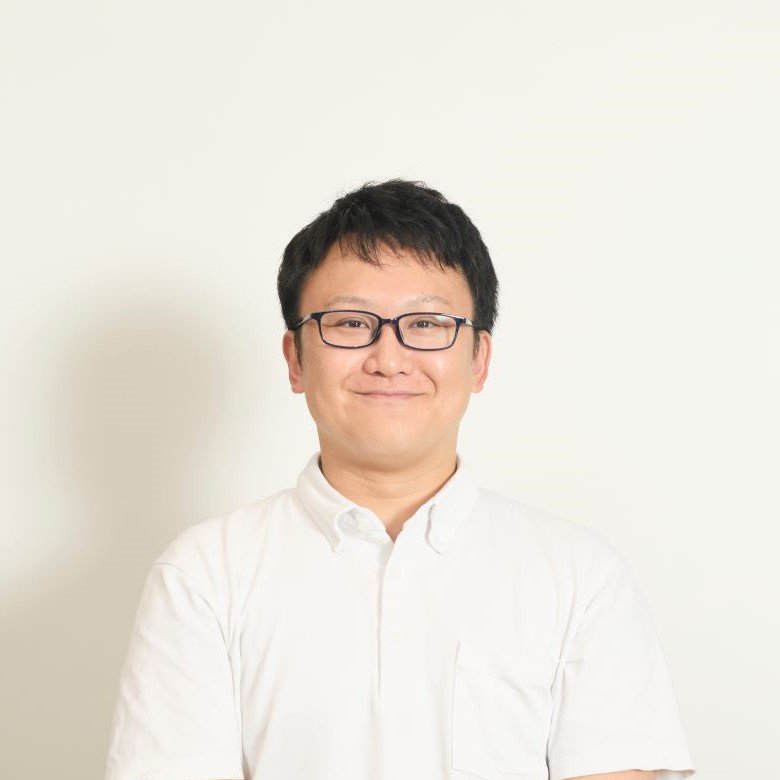
株式会社かんぽ生命保険 サステナビリティ推進部 担当課長
山口 義文(やまぐち よしふみ)さん
2013年、株式会社かんぽ生命保険入社。本社移転プロジェクトや、2021年に日本郵政株式会社へ出向して他社との業務提携などに携わった後、2023年4月から現職。「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」などのイベント運営を中心に担当。

株式会社かんぽ生命保険 サステナビリティ推進部 主査
五日市 祐子(いつかいち ゆうこ)さん
約10年間のNHK「テレビ・ラジオ体操」「みんなの体操」実技出演を経て、2020年、株式会社かんぽ生命保険入社。以来、全国でのラジオ体操イベントの企画・運営や、さまざまな形でのラジオ体操指導を担当。

株式会社かんぽ生命保険 サステナビリティ推進部
谷杉 咲代(たにすぎ さよ)さん
2017年、株式会社かんぽ生命保険入社。社内報の制作などに携わった後、2023年4月から現職。全国小学校ラジオ体操コンクールや、ラジオ体操出席カードの制作、SNS戦略などを担当。
誰もが気軽に実践できることが最大の強み
――まずはラジオ体操の歴史から教えていただけますか。
山口:1925年、当社の前身である逓信省簡易保険局の猪熊 貞治(いのくま さだはる)監督課長が欧米視察中に得た発想をもとに、ラジオを用いた体操事業を日本に紹介したことが発端です。
1928年9月に「ラジオ体操によって国民が健康になり、寿命が伸び、幸福な生活を営むことができるように」という理念のもと、旧ラジオ体操第一が制定され、同年の11月1日からラジオ体操の放送が始まりました。「国民保健体操」の名称で始まったラジオ体操は、当時最新のメディアであったラジオの力によって、広く普及していきました。

――現在のラジオ体操の動作は、どのように決められたのですか。
五日市:体育や音楽などさまざまな分野の複数のエキスパートによって、シンプルでありながら効果的に筋肉を刺激し、なおかつ楽しくリズミカルに体を動かせるように動作が決められました。また、ピアノの音に合わせて動くことも特長です。ラジオ体操の大きな動き、小さな動きに応じて曲調やテンポが明確に変わるので体操がしやすくなっています。これは、先に体操の動作を考え、その後、動作に合わせてピアノ音楽が考えられているからなんです。

――確かに、ラジオ体操のピアノってリズミカルですよね。誰もが気軽に取り組めるように広報活動はどのように行っているのですか。
山口:当社のホームページにラジオ体操の特設ページを設けているほか、チラシやポスターの展開、さらには各都道府県にある支店などの担当者や郵便局、全国各地のラジオ体操連盟などさまざまな方々にもご協力をいただいています。
谷杉:主に若い世代の方々に向けては、SNSでの発信にも積極的に取り組んでいます。そのなかの一つ、会話を見たり参加したりできるSNSのフォロワーは約5万9,000人(2025年2月現在)に及んでいます。近年急速に数が伸びていて、有望なコンテンツになっていますね。

子どもたちの体力づくりを支援する新たなコンテンツも登場
――現在、普及のために行っている取り組みを教えてください。
山口:主に4つ展開しています。
・「巡回ラジオ体操・みんなの体操会」
・「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」
・「全国小学校ラジオ体操コンクール」
・「ラジオ体操出席カード」の制作
まず「巡回ラジオ体操・みんなの体操会」は、例年7月20日~8月31日の間、全国42会場ほどで行う夏期巡回と、夏期巡回の期間を除く5月~10月までの日曜日、全国5会場ほどで行う特別巡回の2つに分かれています。


五日市:「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」は、年に1回、全国のいずれか1カ所で開催するイベントで、NHKのテレビ、ラジオで国内・海外に向けて生放送される点が特長です。ちなみに2024年は北海道旭川市で実施して、2,200人あまりが来場されました。そうしたリアル参加の方々に加えて、テレビを見ている方やラジオを聴いている方も同時に体操していただく、というコンセプトで「1000万人」を冠しています。

谷杉:私は「ラジオ体操出席カード」の制作と「全国小学校ラジオ体操コンクール」を主に担当しています。「ラジオ体操出席カード」は全国の公立小学校の児童数を目安に制作枚数を決めていまして、2024年度は約845万枚を印刷しました。

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
「全国小学校ラジオ体操コンクール」は、ラジオ体操を通じて児童の健全育成を応援するコンクールとして2014年に始まりました。全国の小学校で撮影されたラジオ体操の映像を送ってもらって審査するもので、「技術部門」と「取組部門」の2つの部門があります。まず「技術部門」は、ラジオ体操第一を行っている児童たちの様子を「元気よく楽しんで体操している」「そろった動きで正しく行っている」といった点を意識して撮影していただきます。「取組部門」では、文字どおり、日ごろどのようにラジオ体操に取り組んでいるかを見せていただくものです。例えば「児童が互いに動作を確認し合って、正しい動きをしている」「体操を通じて地域の人たちと交流している」「幼稚園児に教えている」などの風景を撮影していただきます。両部門で毎回400チームくらいから応募がありますね。


――2024年からは谷杉さんが中心になって新たなコンテンツを制作・リリースされたそうですね。
谷杉:はい。小学校の教材として無料でダウンロードしていただける「ラジオ体操教材」です。特長は、ラジオ体操第一を題材にして骨や筋肉の動き方などの人体の仕組みを、体を動かしながら学べること。また、子ども自身がアウトプットできることが大事なので、リズムに合わせてオリジナルの体操を考える項目もあります。一般的に動作が複雑になるほどたくさんの筋肉が動かされるのですが、ラジオ体操はあれだけシンプルな動作にもかかわらず、3分ほどで全身運動ができる優れたエクササイズなのだ、という気づきも得てもらえる教材になっています。

健康状態をチェックするバロメーター的な役割も
――ここからはラジオ体操の運動効果についてお伺いしていきます。具体的に、私たちの体にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。
五日市:全身には約650の筋肉があり、ラジオ体操を正しく行えば、そのうちのおよそ400に刺激を与えられるといわれています。400もの筋肉への刺激をたった3分あまりで完了できてしまうのが、ラジオ体操のすごいところなんです。

――「正しく行えば......」というところがポイントですね。
五日市:そのとおりです。ラジオ体操第一・第二、いずれも動作は13種類。一つ一つの動作には目的があり、それをきちんと理解して動くことで、大きな効果が得られます。
例えば、ラジオ体操第一の最初と最後の運動。同じ運動と思われがちですがまったく別で、最初は「伸びの運動」。腕を上に上げたときに背中をグーッと伸ばします。また、腕だけでなく脚の意識も大切。腕と脚を上下に引っ張り合うように伸ばすことがポイントです。一方、最後の運動はしっかり息を吸って全部吐き切る「深呼吸」である点を知ってほしいですね。詳しくはラジオ体操ポータルサイトの 『サクッと!ラジオ体操』を見ていただくと、正しく行えると思います!

五日市:それから、ラジオ体操には"新しい発見"もあるんです。正しい動作を意識してラジオ体操をした後、筋肉痛などを生じた箇所は、いわば黄色信号がともっていて、まったく所定の動作ができなければ赤信号状態だといえます。
例えば、ラジオ体操第一の2番目「腕を振って脚を曲げ伸ばす運動」の動作。このとき、かかとを上げながら脚を曲げ伸ばすのが正しいのですが、仮にかかとが全然上げられないとしたら、それは「自身の体重を支える脚の筋肉が衰えている」ことを意味します。そういった方は、歩行中の転倒や骨折につながるリスクもある。つまり、ラジオ体操は健康状態の良し悪しを測定するバロメーターでもあるのです。

取り組み方次第でもっと拡大! ラジオ体操には"伸びしろ"がある
――サステナビリティ推進部への配属前後における、ご自身の変化をお聞かせください。
山口:2023年に現部署に異動してからは、もはや業務の100%がラジオ体操に関連したものとなり、その奥深さを知りましたし、国民の健康増進に資することができ、大きな影響を与えられる仕事であると痛感しました。異動前に比べるとラジオ体操に対する見方が大きく変わりました。

谷杉:運動効果もさることながら、人と人をつなぎ、地域の活性化に役立つ「コミュニケーションツール」の側面も大きいんだなって気づきました。
五日市:かんぽ生命入社前は、常に「ラジオ体操が求められている場所」で働いていました。でも入社後は「ラジオ体操に対して関心の低い層をいかに振り向かせるか」が仕事になったわけです。「自分寄りの表現になっていないか」を意識して、相手の方に歩み寄りながらラジオ体操の魅力を伝えることを心がけるようになりました。

――最後に、今後、ラジオ体操がどのような存在になってほしいか、そのために何をしていきたいかを教えてください。
山口:私の願いはもちろん、この先も末永くラジオ体操が今と同じように国民的な体操であり続けることです。そのために大切なのは、大きなマイルストーンとなる2028年の「ラジオ体操100周年」です。この節目に向け、改めてNHKやラジオ体操連盟、全国の自治体など関係するメディアや諸団体と連携し、複数の記念イベントに向けた準備を進めています。
谷杉:私は、ラジオ体操の放送が始まった日にちなんで制定された11月1日の「ラジオ体操の日」を盛り上げる取り組みを強化していきたいと思っています。2024年は初めてSNSで大々的なキャンペーンを実施しましたが、2025年以降も多くの企画を用意して、ラジオ体操を思い出すきっかけづくりを続けていくつもりです。

五日市:「最近野菜不足だな~」と思ったときに、「とりあえず野菜ジュース飲むか」と考える人、多いと思うんですよね。これと同じ図式で、「最近運動不足だな~」となったら「ラジオ体操やるか」と即座に連想していただけるくらい身近な存在になってほしいと思っています。
そして究極の理想は、かんぽ生命、日本郵政グループの関連企業すべての社員が、ラジオ体操の指導者資格を取得すること。ラジオ体操の正しい動きをグループの全社員が身に付け、発信してほしいと思っています。教える人が増えれば、それに比例してラジオ体操をする人はさらに増えるはずだと信じています。

ラジオ体操の歴史に関する記事はこちら!
日本郵政グループのサステナビリティ最前線 連載記事一覧はこちら