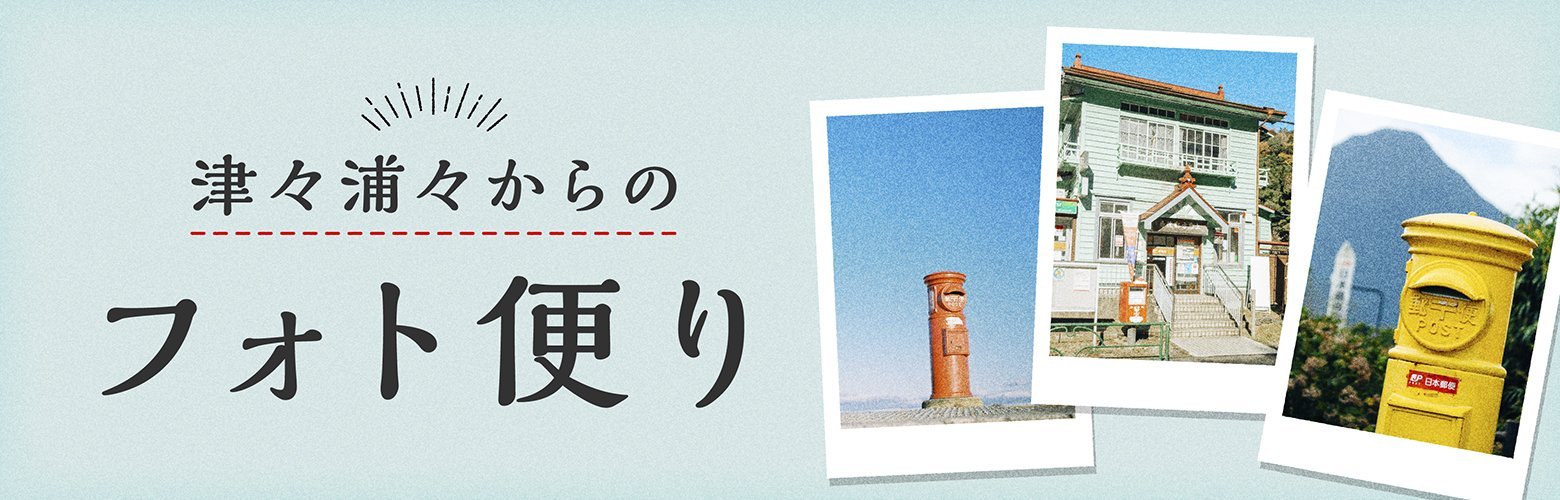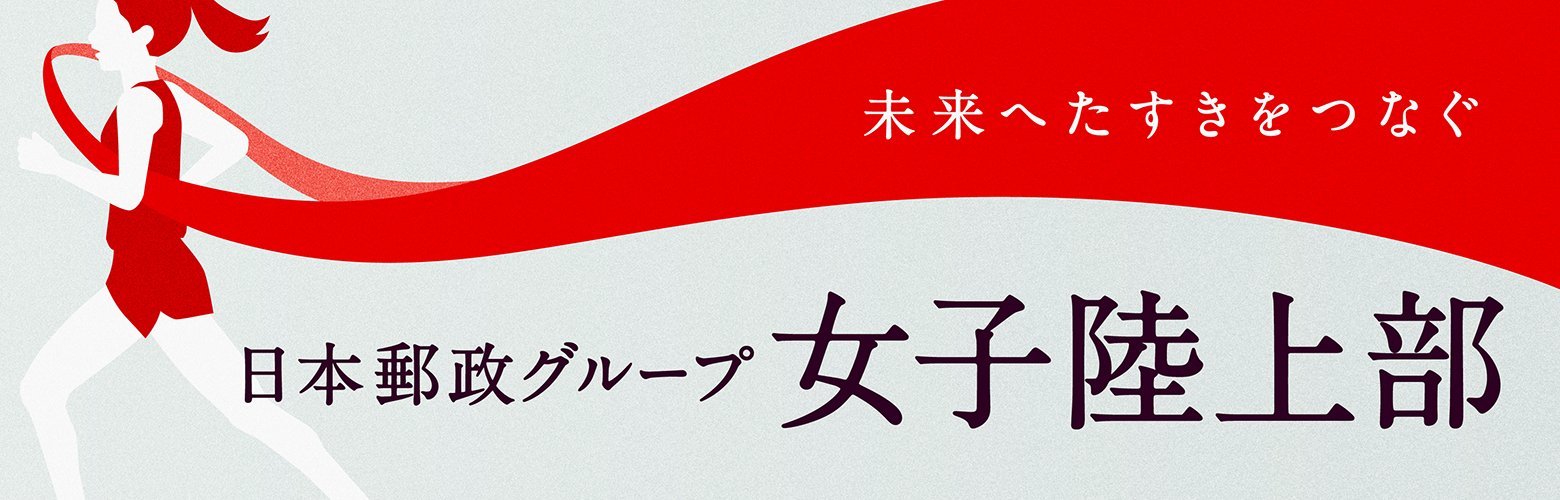カンボジアに高品質な郵便サービスを!プロジェクト担当者が語る"日本型郵便インフラの海外輸出"

INDEX
日本郵便株式会社は、政府の日本型インフラ輸出戦略のもと、UPU(※)、ODA(政府開発援助)、総務省などの施策への参画や海外の郵便事業体からの直接の業務受託を通じて、2014年にミャンマー、2015年にはベトナム、2015年以降は東南アジア、南西アジア、東欧、中東諸国などにおいてさまざまな取り組みを行っています。その成果がUPUや海外の郵便事業体から評価され、2021年からUPUのカンボジア郵便の業務改善プロジェクトが始動しています。
今回は、カンボジア郵便の業務改善プロジェクトメンバーである輸送部の加治佐 洸介(かじさ こうすけ)さんと、これまで数々の国際協力プロジェクトに携わってきた国際郵便事業部の遠藤 洋子(えんどう ようこ)さんに、日本型郵便のインフラ輸出とはどういうものか、カンボジアでの取り組みなどを交えながらお話しいただきました。
※UPUとは、Universal Postal Unionの略。192の国・地域の加盟国からなり、世界の郵便制度を統括している国際連合の専門機関の一つ。

日本郵便株式会社 輸送部 係長
加治佐 洸介(かじさ こうすけ)さん
2013年、日本郵便株式会社に入社。2014年から本社輸送部で6年間勤務。その後、郵便局勤務を経て、2021年より再び本社輸送部に配属となり、他社との協業などを担当。

日本郵便株式会社 国際郵便事業部 係長
遠藤 洋子(えんどう ようこ)さん
当時の郵政省に入省後、海外赴任を含め、これまでに多くの国際プロジェクトに従事。2018年より日本型郵便インフラの海外輸出を担当。
日本型郵便インフラの海外輸出とは?
日本では郵便物がお客さまと約束した日数で確実に届くのが当たり前ですが、世界の新興国では、何日経っても届かない、今どこにあるのかも把握ができないといったことなど、郵便業務に問題を抱える国は少なくありません。そこで近年、世界においても高品質を誇る日本の郵便業務のノウハウや関連技術を、各国に提供する動き(=日本型郵便インフラの海外輸出)が進んでいます。
「日本郵便には、創業以来150年余りにわたり培ってきた高品質な郵便業務のノウハウがあります。その仕組みを提供し、その国の郵便サービスの改善や品質向上、さらには両国の友好関係を構築し経済成長につなげていくこと。それが、日本型郵便インフラの海外輸出の目的です。
郵便オペレーションの効率化、品質が向上することで、近年飛躍的に成長するeコマース(ネット通販)への対応も可能になりますし、お客さまからの信頼も確保され、日本からの郵便物も確実にお届けできることで、アジア市場の拡大を目指す日本の企業活動においても、そのメリットは大きいと言えます」(遠藤さん)

カンボジア郵便を変えた、日本郵便の力
郵便物の輸送に関する専門家としてカンボジア郵便の業務改善プロジェクトに参画した加治佐さん。現地の郵便局が抱える問題とはどのようなものだったのでしょうか。

「カンボジア郵便からは、郵便局内の作業遅延と従業員の身体的負担を改善したいという要望がありました。そこで、非効率なオペレーションの改善を図るために提案したのが、日本郵便で使用しているロールパレット(荷物を囲むための格子状の枠が付いている運搬用の台車)とフリーローラー(運搬用の大型ローラーコンベア)の導入です。
カンボジアの郵便局では郵便物の保管や仕分け作業などが床の上で行われており、トラックに郵便物を積み込むのも一つ一つ手で持ち上げて運ぶ重労働の繰り返しでした。
ロールパレットなどを使えば、オペレーションの効率化が図れるのはもちろん、荷物の汚れや破損リスクを減らせますので品質向上にもつながります。作業スピードがアップしただけでなく、足腰に負担をかけず安全に作業ができるようになったことで現場の方々にとても喜んでいただきました。
また、荷物の汚れや破損リスクが低下したことで、お客さまのCS向上にも貢献できました。
それぞれの国や環境によってできること、できないことがあるので、日本郵便の仕組みやノウハウをカンボジア郵便に馴染む形に落とし込む作業が一番大変でしたが、やりがいを感じるところでもありましたね」(加治佐さん)




「アジアの国々では、床上作業がオペレーションの遅れ、品質の劣化につながっているケースが多いです。
ベトナムの場合も、2015年からコンサルティングをしているのですが、当初は、床上作業が行われていました。ベトナムからオペレーション近代化を支援してほしいとの相談があり、プロジェクトが始まりました。
床上作業をやめ、ロールパレットの導入などを行うことで作業効率を改善することに加えて、先方の要望により、オペレーション人材の育成にも力を注ぎました。
その成果は、送達日数の短縮、小包破損率の大幅な低下などにつながり、ベトナム郵便からも大いに感謝されています。そして次なる相談も現在寄せられている状況です」(遠藤さん)

さらに、今回のカンボジアでは、郵便局間を結ぶ輸送ラインの改善も大きな課題だったと言う加治佐さん。どのような改善を行ったのでしょうか。
「現地調査では、首都プノンペンにあるプノンペン中央郵便局からアンコールワットで有名な観光都市シェムリアップの郵便局までの実際の輸送ルートを確認しました。往復13時間の長距離移動は体力的に大変でしたが、実際の道のりをリアルに把握することができたおかげで、夜間に運送便を走らせるアイディアが生まれました。これにより、送達スピードが半日から1日速くなる改善につながりました」(加治佐さん)

高品質を誇る業務ノウハウ・技術を提供し、国際貢献を果たす
日本型郵便インフラを海外へ輸出するプロジェクトには、海外郵便事業体からの直接の業務受託、UPUなどの国際機関プロジェクトやODA、総務省調査研究などの政府機関からの業務受託というチャネルがあるそうです。
「カンボジアの案件はUPUから要請をいただいたのですが、それはミャンマーやベトナムで行った業務改善の成果が国際的に評価されてのこと。日本郵便の国際貢献が認められたことはとても光栄に思います」(遠藤さん)

日本型郵便インフラの海外輸出という国際協力プロジェクトでは、日本郵便の仕組みやノウハウを提案・提供することはもちろん、大切なのは、その国の郵便事業に携わる人々が主体的に改善をしていく意識を持つことです。
「日本郵便には、お客さまとお約束した配達日数を守るために『結束』という考えがあり、その結束を遵守するために、各セクションでの作業時間がきっちり決まっています。カンボジアの郵便局内でも、今では『ケッソク』という日本郵便の用語が、合い言葉のように飛び交っています。
そうした現地で働く方々の変化を見ると、単に効率化、スピード化を進めるのではなく、なぜそうしなければならないのか、郵便事業の役割と責任を理解していただき、共有できてこそ、大きな成果につながるということを改めて実感します」(加治佐さん)
「これまでさまざまな国の郵便事業を支援するプロジェクトにかかわってきたなかで、一番難しく苦労する点は、相手国の文化や価値観を尊重しながら、話し合いを重ね、折り合いをつけていくこと。国が違えば、価値観や感覚の違いがあるのは当然です。そういう互いの違いや壁を乗り越え、協力してよりよい郵便サービスを実現できたときの達成感は本当に大きいものです」(遠藤さん)

最後に、日本郵便の力を海外に提供する国際プロジェクトに携わるお二人に今後のビジョンを伺いました。

「私は国内の幹線輸送を専門に扱う部署に所属しているので、日本郵便の幹線輸送効率をさらに向上させるのが今後の目標です。高齢化によるトラック運転手の減少やトラック運転手の時間外労働の上限規制は、物流会社の深刻な課題で、これからは他社との協業・協力がより重要になっていくと思います。
今回、カンボジア郵便の業務改善プロジェクトを通して、言葉・文化・価値観の異なる方々に日本郵便の仕組みや輸送方法を理解していただき、相手に馴染む形で落とし込むことにより成果につながった経験を、他企業と協業した輸送ネットワーク作りに活かしていきたいと考えています」(加治佐さん)
「郵便業務に問題を抱えている国はアジアだけではなく、世界にはまだまだ日本郵便のノウハウを必要としている国がたくさんあります。そうした国々への日本型郵便インフラの輸出を通して、日本の高品質な郵便サービスを世界中に広げていくことで、国際貢献が果たせたらと思っています」(遠藤さん)