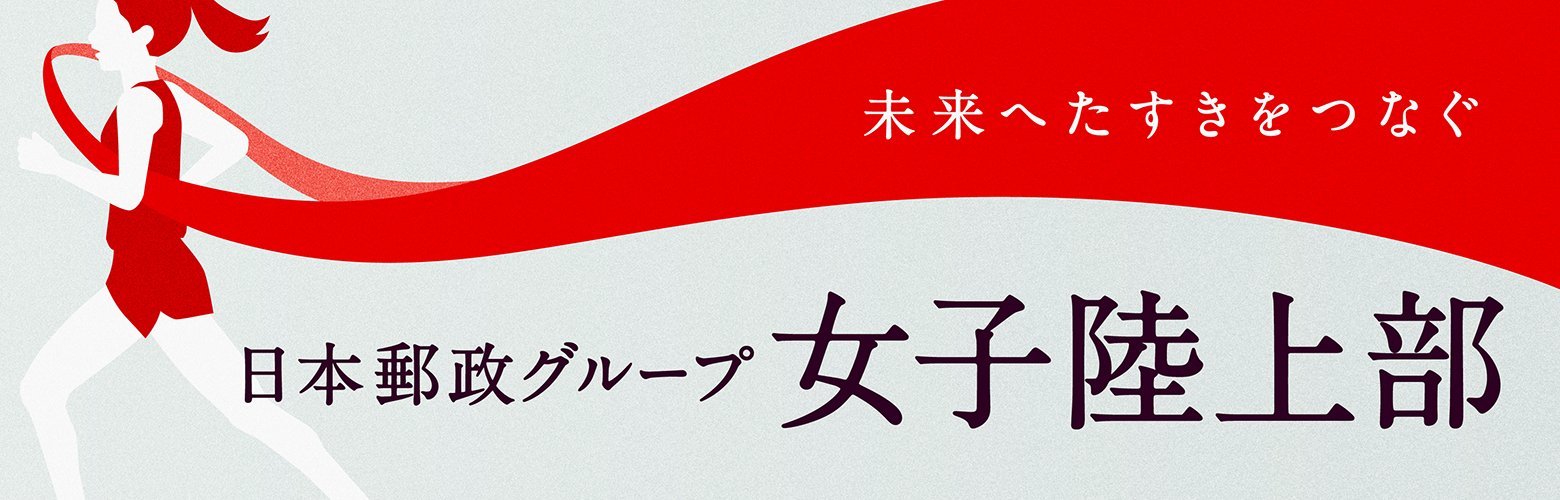ローカル共創のススメVol.9 未知の種を見つけ、その種をまき、育てられる「作り人」に

INDEX
「地域(ローカル)」をフィールドとしたプロジェクト、「ローカル共創イニシアティブ」※で各地に赴任している社員を紹介する本企画。
第9回は、2023年4月から株式会社エーゼログループを協業パートナーとして、北海道は道央南部に位置する厚真町(あつまちょう)に出向し、同地域で活動する濱田 真基子(はまだ まきこ)さんを取材。濱田さんの取り組みとかかわりが深い、厚真町役場の小松 美香(こまつ みか)さん、エンカレッジ株式会社の花屋 雅貴(はなや まさたか)さんにもお話を伺いました。
※公募により選出された日本郵政グループの若手・中堅社員を、社会課題に先行して取り組む地域のベンチャー企業や地方自治体に2年間派遣することにより、新規ビジネスなどを創出することを目指すプロジェクト

日本郵政株式会社 事業共創部 マネジャー
濱田 真基子(はまだ まきこ)さん
2011年、郵便事業株式会社(当時)に入社。2023年4月から厚真町へ出向中。以前は物販ビジネス部でフレーム切手などの商品開発を担当していた。

厚真町役場 まちづくり推進課
小松 美香(こまつ みか)さん
2018年、厚真町役場に入職。地域おこし協力隊制度やローカルベンチャースクール、二地域居住の推進にかかわる取り組みを主に担当。

エンカレッジ株式会社 代表取締役
花屋 雅貴(はなや まさたか)さん
株式会社エーゼログループで現地責任者として、厚真町とともにローカルベンチャースクール事業に携わる。2023年にエンカレッジ株式会社を設立、現在は組織作りの支援に取り組む。東京都と北海道の二拠点生活を経て、2024年2月より厚真町民に。
仕事への向き合い方に変化。週末は家庭菜園や登山で地域の人々と交流
――濱田さんが「ローカル共創イニシアティブ」に応募された動機を教えてください。
濱田:2022年度までは本社で「オリジナル フレーム切手」の商品開発を担当していました。日本全国の観光名所などをテーマにしたフレーム切手を作って、販売するものです。そういった経験から、郵便局は地域に詳しい存在だという自負があって、地域の郵便局をもっと活用する方法はないかという想いを抱いていました。そんなとき、ローカル共創イニシアティブの公募を知り、「想いを形にするチャンスだ!」と、挑戦してみようと思ったんです。

――出向先として北海道厚真町を選んだのはどうしてですか。
濱田:候補地の多くは、農福連携や空き家活用といったテーマがあらかじめ決まっていましたが、厚真町は具体的なテーマが決まっていませんでした。自分で地域の現状や課題を見てからテーマを決めたいという考えがあったので、厚真町を選びました。
――皆さん道外ご出身だそうですが、厚真町のどんなところに魅力を感じますか。
濱田:厚真町は自然が豊かでのんびりとした空気を味わえるのですが、空港が近くて、車で30分も走れば苫小牧や千歳などの都市部にもアクセスできます。それは、厚真町の住みやすさであり魅力だなと感じます。

小松:私も同じことを感じます。それだけでなく、厚真町はローカルベンチャー推進事業※をやっていることもあって、町民の挑戦を応援する雰囲気があり、起業したり、やってみたいことを始める文化が醸成されてきたという感触があります。
花屋:例えば、起業して一次産業で何か事業を行おうと思ったときに、札幌までが直接的な商圏になるのも、厚真町の大きな強みですね。
※厚真町では移住・定住施策として、2016年から厚真町での起業を目指す起業家人材を育成することで、地域での新規事業の立ち上げや新規雇用創出などを促進し、地域経済活動の活性化を図る「ローカルベンチャー推進事業」を行っている
――一方で、厚真町の課題だと感じるのはどんなところですか。
花屋:過疎化や高齢化が進んでいるのはどの地域も同じで、特に北海道ではインフラ維持の課題はどこもいっしょです。ただ、そのレベルでの"課題"という言葉には、僕らはあまり興味がないんですよね。その点は、きっと濱田さんが厚真町に来て結構困ったところじゃないかなと思います。
濱田:そうですね。厚真町の課題を設定するのはすごく難しいと感じました。花屋さんから「視点を変えて一人ひとりを応援する方向性のほうがいいのでは」と、アドバイスをもらいました。そこで、ローカルベンチャーで起業した人たちに積極的に会うことにしたんです。
花屋:地域に溶け込むためには、やはり地域の人を知る必要があります。だから、実際に話を聞かせてもらって、それを記事にして発信することでコミュニケーションがとれるのではと考え、濱田さんに提案しました。
――濱田さんは、厚真町で働くようになってから仕事への心構えや考え方などで、変化はありましたか。

濱田:出向前は、決まった仕事や、ある程度マニュアルがある環境での業務に携わっていました。でもここでは、自分で考えて動かないと仕事が進みません。資料の作成にしても、途中で誰かに確認や相談することがないので、最初から完成形を作らなければいけない。そういう意味では、仕事一つひとつに対しての意識の向け方が変わりました。

――生活や気持ちの面などで変化したことはありますか。
濱田:やりたいと思っていたことがいろいろできています! 趣味の面で言うと、家庭菜園を始めました(笑)。ほかには、地域住民の方が主催している「山の会」に入って登山も始めたんです。毎週末のように日帰りで行ける北海道の山に登っていて、そこでも人脈が広がりましたね。
小松:出会って最初のころ、濱田さんは"会社の枠にはまった人"という印象でした。でも、次第に地域の人たちと家庭菜園や登山をしたり、バーベキューをしたりといった経験を重ねて、だんだんとゆるんでほどけてきたのかなと、近くで見ていて感じています。
濱田:「肩の力抜いてください」って、30回くらいは言われましたね(笑)。
花屋:濱田さんが会社に求められていることをやろうとしても、僕らは「そのままやっても意味ないかも」といった感じで反応するから、濱田さんは何をすべきかわからなくなるんでしょうね。そういうことに対応するなかで仕事をする姿勢も変わっていったのかなと思います。

情報発信や郵便局への橋渡しで、地域と人を支える

――厚真町で濱田さんが取り組まれてきたことを教えてください。
濱田:最初に取り組んだのは、「ふるさと納税の返礼品の発送コスト削減」です。もともと厚真町は、返礼品の発送でゆうパックをメインに利用している地域だったので、郵便局の営業担当と連携して、一部の作業を苫小牧郵便局で行うことで年間約200万円の物流コストを削減することができました。
花屋:そのほかに、先ほどお話しした厚真町で起業した人などを取材して記事にすることを濱田さんにやってもらって助かりました。
――先ほどもお話がありましたが、記事作りについて教えてください。
濱田:『ATSUMA-NOTE(あつまのおと)』というエーゼログループが厚真町から受託し、厚真町の「ヒト・コト・モノ」、そして「挑戦と出会い」を発信しているWebサイトがあるのですが、旬の話題としてローカルベンチャー事業で活動されている方を取材して、月に2本のペースで記事を書いていました。

――それまで取材をして記事を書く経験はあったのですか。
濱田:初めての経験でした。だから、取材して書いた記事をまずは花屋さんに見てもらい、さらに町役場の小松さんのチェックを経て掲載するという、一連のサポートを受けながらの挑戦でした。しっかりとヒアリングをして記事にするので、おのずと相手のことを深く知ることができましたし、取材をきっかけに親交が深まった方もいました。
花屋:記事作りって「何を捉えて、何を書くか」のポイントがずれると大変なんですが、濱田さんは最初からつかんでいました。枝葉のところだけ少し手を加えれば大丈夫だったので、とてもセンスがいいなと思いました。

――起業した方たちと郵便局との橋渡し的な役割もされているそうですね。
濱田:郵便局を訪問して、ローカルベンチャーに携わる方を紹介したり、どんな活動があるのか内容を伝えたりと、「人」と「情報」をシェアする役割を担っています。
厚真町における濱田さんの活動について、厚真郵便局の伊藤 景一(いとう けいいち)さんにお話を伺いました。
厚真郵便局
伊藤 景一(いとう けいいち)さん

厚真町で新しくお店や事業を始めている方のところに頻繁に足を運んで意見交換や情報交換を熱心にされていて、つながりを作ること、橋渡しをすることが上手な方だと思いました。郵便局としても、ローカルベンチャーに携わる方々とつながることで厚真町の魅力をもっと発信できると考えています。濱田さんに橋渡しをしていただきながら、ローカルベンチャーに携わる方々と深い関係を築き、これからも厚真町をいっしょに盛り上げていきたいですね。

――橋渡し役をすることで気づいたことはありますか。
濱田:郵便局とローカルベンチャーの方たちとの"距離"が遠いと感じました。起業した皆さんは業種も労働環境も多種多様で、例えば郵便局が提供するサービスのなかで物流や物販という切り口だけを活用する、としてしまうと郵便局との接点がなくこぼれ落ちる業種が出てきます。そのような理由から具体的な支援内容を決めるのがとても難しかったため、現時点で具体的な取り組みに至らなかったことは反省点だと考えています。

――小松さんと花屋さんは、郵便局をはじめとする日本郵政グループと連携することで、地域にどのような可能性やメリットが生まれると思いますか。
小松:どの地域でも過疎は進んでいるなか、お店などがないところにも郵便局があるのはすごくいいと思います。だから、郵便局が持っているリソースを使えるといいですよね。例えば、郵便配達員は空き家をある程度、把握していると思うんです。厚真町には不動産屋がないので、郵便局が「あそこの家は空いているよ」といった感じで、家を探している人と空き家をつないでくれるサービスがあるといいなと思います。
花屋:僕はこれから会社で人を採用していきたいと考えているのですが、人材という点でも期待したいです。例えば濱田さんに取材原稿や調べもの、資料作成をお願いすると、上の人たちも納得させることができる、精度の高いものがパッと出てきます。今は副業解禁の流れがあるので、日本郵政グループで働く方々が持っているスキルが提供されるようになると、ずいぶん助かると思いました。

厚真町の人たちをつなぎ、いろいろな仕事ができる"作り人"に
――濱田さんは厚真町での任期も残りわずかですが、やり遂げたいことはありますか。
濱田:近々、花屋さんが人を雇って仕事を任せ、事業の組織化を試みる予定なので、私もサポートに入ります。あとは、厚真町のフリーペーパーを制作したいですね。厚真町には個性豊かな人たちがたくさんいます。そんな皆さんに出会ってエネルギーをたくさんもらったからこそ、自分も頑張れていると感じます。それは厚真町の魅力でもあるので、そういった方々を紹介するものをぜひ作ってみたいです。

――『ATSUMA-NOTE(あつまのおと)』で培ったものを活かせますね!
濱田:そうですね。記事作りや情報発信の延長線でもありますし、ローカルベンチャーの方たちとつながってきた集大成になるかなと思っています。
――これから、厚真町での経験をどう活かしていきたいですか。
濱田:これまでは、結論ありきというか落としどころがあって、そこを埋めるような考え方で仕事をしていました。ですが、厚真町ではゴールがわからないからこそ、今までの経験を一回置いておかなくちゃと感じています。花屋さんに教わったんですが、今までやったことのない仕事にも取り組み、土地と向き合い、将来につながる種をまく"作り人"にならなきゃと思います。

――これまでにない2年間で得たものは大きかったのではないでしょうか。
濱田:厚真町で2年間やってみて、"こういう経験が必要"という気づきがありました。会社にプラスになるように持ち帰って提言したいと思っています。

――将来の目標をお聞かせください。
濱田:出向期間が終わったあと、どう厚真町とかかわるかは私次第かなと思います。日本郵政グループの一員として地域とどうかかわり続けられるか。任期中に道筋は立てたいですね。

ローカル共創のススメ 連載記事一覧はこちら