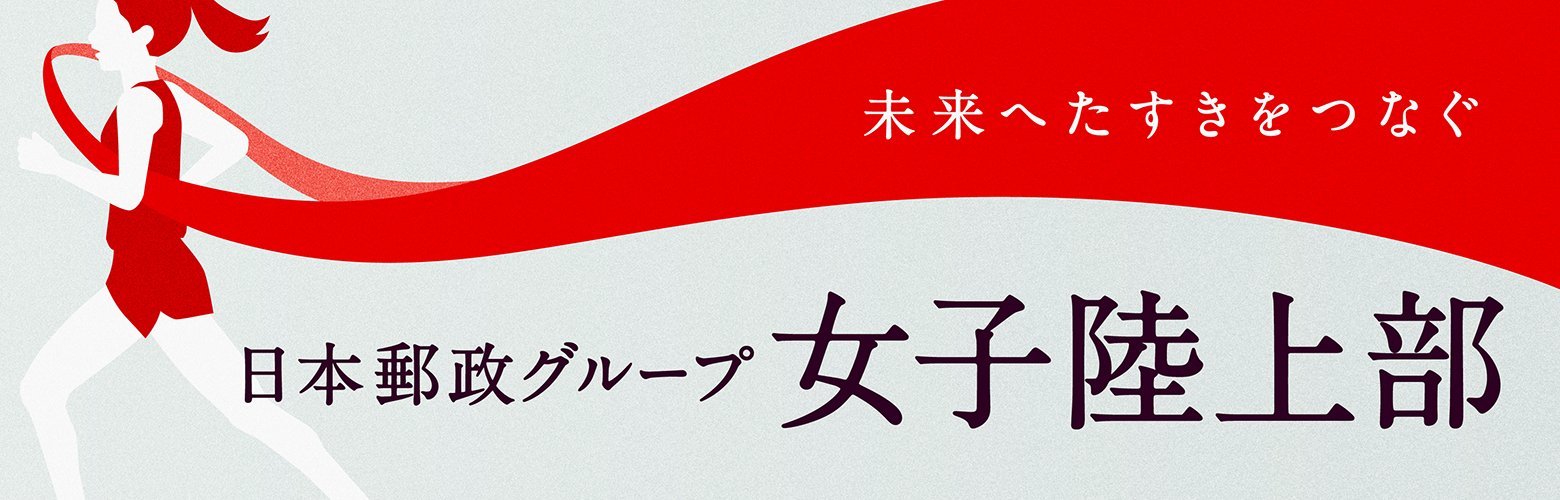担当者が熱血解説! Vol.6 数学的手法やAI技術を駆使してデータを分析し、投資をサポートするプロ「クオンツ」

INDEX
先の見えづらい金融の世界では、リスクを読み通す技術や知見が必要不可欠と言われています。この不確実性に対して、人間の勘や感覚ではなく、高度な数学の知見を駆使して立ち向かうのが「クオンツ」という仕事です。今回は、そのクオンツの業務内容や魅力について、株式会社ゆうちょ銀行の立石 憲男(たていし のりお)さんと、永井 翔太(ながい しょうた)さんに熱血解説してもらいました。
【今回のナビゲーター】

株式会社ゆうちょ銀行 市場統括部 総合クオンツ室 専門役
立石 憲男(たていし のりお)さん
IT関連の仕事と並行して大学院でファイナンスについて修学。2016年、ゆうちょ銀行に入社。総合クオンツ室の立ち上げに携わる。

株式会社ゆうちょ銀行 市場統括部 総合クオンツ室 専門役
永井 翔太(ながい しょうた)さん
証券会社、銀行でクオンツ業務やトレーディング業務に携わった後、2021年、ゆうちょ銀行に入社。さまざまな投資業務を、データの定量分析(※)によってサポートしている。 ※数値で表せるデータをもとに客観的な評価を行う分析手法
Lesson1 「数値」で企業を支えるプロフェッショナル
「クオンツ」という仕事をご存じでしょうか。クオンツとはQuantitative(数量的)という英語から派生した言葉。その名のとおり、「数値」で企業を支えるプロフェッショナルです。
立石:クオンツとは、高度な数学的テクニックや数理モデルを駆使して、金融分野におけるさまざまな市場や商品、投資戦略に対する分析を行ったり、予測モデルを開発する業務に携わる人のことを指す用語です。

会社の業態や特性によってクオンツの役割も異なってくるそうですが、ゆうちょ銀行ではデータの定量分析(数値で表せるデータをもとに客観的な評価を行う分析手法)によって、社内の投資部門を手助けする役割を担っています。
永井:当社には、債券投資部やクレジット投資部、不動産投資部など、さまざまな投資部門が存在しています。そういった部署の担当者が、例えばいま当社が保有しているアセット(「資産」のこと。ここでは投資している対象の資産を指す)にどれくらいリスクがあるか知りたいだとか、これからどういった銘柄に新しく投資したらいいかわからないなど、投資に関する課題を抱えたときに、さまざまなデータを定量分析して、判断材料となる数値を提供するのが、私たちの主な役目です。

では、クオンツの分析結果が、投資部門では具体的にどのように活かされているのでしょうか。クレジット投資部の峠 健士(とうげ たけし)さんは、次のように話します。
株式会社ゆうちょ銀行 クレジット投資部 担当部長
峠 健士(とうげ たけし)さん

クレジット投資部は、国内外の企業が発行する債券等に投資し、クレジット(企業の信用)に係るリスクを取得しながら収益を上げている部署です。私たちは、総合クオンツ室の知見を活かしてポートフォリオ(投資銘柄の配分の組み合わせ)のリスクを見える化し、金利リスク・クレジットリスク・為替リスクなどが投資方針に沿った量になっているかを確認しています。また、新規投資の検討にあたっても、投資候補先のリスク量や既存のポートフォリオ全体への影響などについて、総合クオンツ室に分析を依頼して、その結果を投資判断に活かしています。
まだまだ一般的には聞きなじみのない仕事かもしれませんが、クオンツの存在感は近年になってますます増していると立石さんは言います。

立石:金融業界に数学・統計学を用いた定量分析が取り入れられるようになったのは、1970年代からと言われています。従来、金融業界では人間の勘や感覚のようなものによって投資判断がなされてきましたが、欧米では1970年代から金融工学の研究が発展し、勘や感覚に頼らず、定量的な数値データの分析から投資や運用を行うようになりました。日本でクオンツが広まってきたのは、ここ20年くらいのことですが、近年はAI技術の進歩によって投資予測や分析技術が高度化しているので、そのAI技術を駆使してデータ分析を行うクオンツの重要性はますます高まっています。当社でも、運用の高度化・多様化を見据えて、2016年にクオンツ業務を専門とする「総合クオンツ室」を設置しました。
専門性の高い仕事であるために、クオンツとして活躍するには高度なスキルが求められます。
立石:やはり数学的な分析能力は重要ですし、計算するためのシステムを開発することもあるため、プログラミングなどのIT技術も求められます。また、クオンツの論文はほとんど英語なのでそれを読んだり、仕事で海外の人とやり取りしたりすることもあるため、英語のスキルも必要です。
また、永井さんはクオンツに向いている人の資質として「忍耐力」「好奇心」の有無を挙げます。
永井:クオンツ業務は、地道な試行錯誤の繰り返しです。一つの課題を解決するために、数式のモデルを考えて、実際にプログラムを組んで検証して、その結果から改善策を考えてまた検証して......。正直、95%はうまくいかないことばかりですが、そこで投げ出すのではなく、何度もチャレンジして答えを導くだけの忍耐力、また、答えを「知りたい」という強い欲求、好奇心がクオンツには必要なのかなと思います。

【ここがポイント!】
クオンツは数学、IT、英語のスキルを駆使し、忍耐と好奇心をもって投資の課題を解決するプロ!
Lesson2 数学のスキルでビジネスに貢献できる、やりがいの大きな仕事
クオンツのやりがいについて、立石さんと永井さんは「数学の知見を活かして、ビジネスや社会に貢献できること」だと口をそろえます。
立石:自分で仮説を立て、分析して答えを導き出すというプロセスも重要ではありますが、私たちは学者や研究者とは違います。やはり自分が作ったモデルを社内の運用担当者に活用してもらい、ビジネスに貢献するといったところに、一番のやりがいを感じます。

永井:学校だと数学は「勉強して将来何の役に立つの?」と思われがちな科目だと思うのですが、クオンツ業務をしていると、まさにその数学の知識や経験を活かして、実社会へ貢献できていることを実感します。また、当社は資産の運用額が約240兆円(2024年12月末時点)と日本有数の規模を誇る企業です。これだけ大きな資産の運用に寄与できるという点は、当社のクオンツだからこその魅力なのかなと思います。
また、クオンツの経験がプライベートで活かされることもあるのだとか。
立石:数値を分析するということに慣れているので、自分で個人資産を運用するときにも定量分析を活用しますし、スマートウォッチなどで取得した睡眠データや運動データを分析して、日ごろの体調管理にも活かしています。
永井:私もデータを集めて分析するということが好きなので、いまプライベートで子どもの睡眠時間や食事の量を記録して、そこから法則を導き出せないかと試みています。将来的に、家庭での育児のストレス緩和に役立てる、そんなことができたらいいなと思います。

【ここがポイント!】
240兆円規模の資産運用に寄与することができるやりがいの大きな仕事!
Lesson3 業務環境を整備し、さらに収益拡大に寄与していきたい

立石:総合クオンツ室は当初、マイクロソフトのオフィスのみインストールされているノートパソコン1台が机に置かれているだけ、という状態からスタートし、ゼロから環境を構築してきました。計算に必要なサーバーの増設など、今後も業務環境の整備は推進していく必要があると感じています。そのためには予算が必要ですし、予算を得るためには、成果を出して社内でさらに認められていかなければならない。実績を出し、得られた予算で環境を構築し、さらに大きな成果を得るという好循環を生み出していきたいですね。

永井:理論上、当社の収益性にはまだまだ伸びしろがあると考えています。これからも収益拡大に寄与し、社内の信頼を一層獲得していきたいですね。しかし、クオンツという仕事の性質なのか、どうしてもストイックで職人的な、近寄りがたい存在として見られてしまうことがあるようで(笑)。そういうイメージをあまり持たれないよう、普段から社内でのコミュニケーションは大事にしていますし、チーム内でもくだらない話をいっぱいしていますので、ぜひ気軽に話しかけてほしいですね。

【ここがポイント!】
社内でも新しい組織だからこそ、ゼロから作り上げていく面白さがある!
▶舞台裏で見つけたもの
- クオンツは、高度な数学の知見を用いて、リスクを予測するプロフェッショナル
- 近年はAI技術の進歩により、クオンツの分析技術が高度化し、ますます求められる重要な存在に!
担当者が熱血解説! 連載記事一覧はこちら